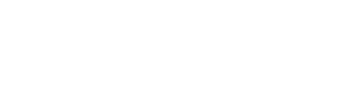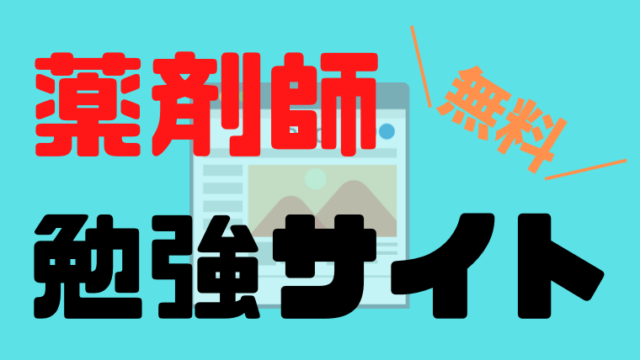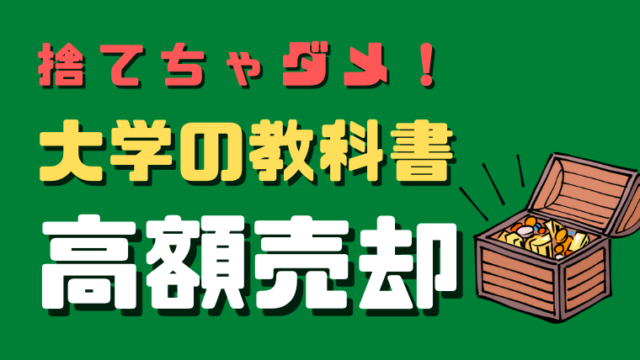どうもヤクタマです。
「薬歴の書き方がわからない」「SOAPって何を書けばいいの?」「先輩に指摘されるポイントが多すぎる…」
薬剤師として働き始めたばかりの頃、誰もが経験する悩ですね。
薬歴作成は薬剤師業務の中でも特に重要でありながら、学校では十分に習得できないスキルです。
本記事では、新人薬剤師の皆さんに向けて、薬歴の基本的な書き方からSOAP形式での記載方法、実際の記入例まで、現場ですぐに活かせる知識を徹底解説します。
薬歴とは?その重要性と基本構成
薬歴(薬剤服用歴管理指導記録)は、単なる事務的記録ではありません。
患者さんの医療情報を集約し、適切な薬学的管理と服薬指導を行うための重要な臨床ツールなのです。
薬歴の3つの役割
- 法的記録としての役割
- 薬剤師法第25条の2に基づく法的義務
- 調剤報酬算定の根拠資料
- 医療過誤発生時の証拠資料
- 医療情報共有ツールとしての役割
- 薬剤師間の情報共有
- 多職種連携における情報提供
- 患者さんへの説明資料
- 薬学的ケアの記録としての役割
- 薬学的評価と問題点の記録
- 服薬指導内容の記録
- 薬物治療の効果と副作用のモニタリング
薬歴に記載すべき基本情報
薬歴には、以下の基本情報を必ず記載する必要があります:
- 患者基本情報(氏名、生年月日、性別、保険情報など)
- アレルギー歴・副作用歴
- 既往歴・現病歴
- 併用薬・健康食品情報
- 生活習慣(喫煙、飲酒など)
- 妊娠・授乳情報
- 来局時の患者の状態
- 処方内容とその評価
- 服薬指導の内容
- 次回来局時の確認事項
これらの情報を整理して記録することで、継続的かつ質の高い薬学的ケアを提供することができます。
SOAP形式による薬歴記載の基本
現在の薬局実務では、SOAP形式での薬歴記載が主流となっています。
SOAP形式とは、患者情報を「Subjective(主観的情報)」「Objective(客観的情報)」「Assessment(評価)」「Plan(計画)」の4つの要素に分けて記録する方法です。
SOAP形式のメリット
- 情報の整理がしやすい
- 薬剤師の臨床思考プロセスが明確になる
- 他の薬剤師が見ても理解しやすい
- 問題点と対応策が明確になる
SOAP各要素の基本
| 項目 | 内容 | 記載例 |
|---|---|---|
| S (Subjective) | 患者さんから聞き取った情報 | 「頭痛が続いている」「薬を飲み忘れることがある」 |
| O (Objective) | 客観的に確認できる情報 | 処方内容、臨床検査値、バイタルサイン |
| A (Assessment) | 薬学的評価、問題点の抽出 | 「服薬コンプライアンス不良」「副作用の可能性」 |
| P (Plan) | 薬学的ケアプラン、対応策 | 「一包化の提案」「副作用モニタリング」 |
SOAPの各要素をバランスよく記載することで、薬学的管理の質を高めることができます。次のセクションから、各要素の具体的な書き方について解説します。
【S】Subjective:患者情報の収集と記録のコツ
Subjectiveは、患者さんから直接聞き取った情報や訴えを記録する部分です。新人薬剤師がつまずきやすいポイントでもあります。
効果的な情報収集のコツ
- オープンクエスチョンから始める
- 「最近のお体の調子はいかがですか?」
- 「お薬を飲んでみてどうでしたか?」
- クローズドクエスチョンで詳細を確認
- 「頭痛は毎日ありますか?」
- 「痛みは何時頃発生しますか?」
- 症状を具体的に聞き出す
- いつから(When)
- どこが(Where)
- どのように(How)
- どのくらい(How much)
Subjectiveに記載すべき項目
- 体調・症状に関する訴え
- 薬の効果実感
- 副作用と思われる症状
- 服薬状況(飲み忘れなど)
- 生活習慣の変化
- 市販薬・健康食品の使用状況
- 患者さんの不安や疑問
記載例
S:
「ロキソニンを飲むと胃が痛くなる」と訴えあり。痛みは服用後30分程度で発生し、1〜2時間持続するとのこと。食後に服用しても同様に発生。先週から市販の整腸剤も服用しているが改善なし。「胃薬も処方してもらえないか」と希望あり。
このように、患者さんの言葉をできるだけそのまま引用し、具体的な状況がわかるように記録することがポイントです。
【O】Objective:客観的情報の適切な記載方法
Objectiveは、薬剤師が客観的に確認できる情報を記録する部分です。処方内容や検査値など、事実に基づく情報を記載します。
Objectiveに記載すべき情報
- 処方情報
- 処方薬とその用法・用量
- 処方変更点(増量、減量、追加、中止など)
- 処方日数
- 検査値・バイタルサイン
- 血液検査値
- 血圧、脈拍
- 体重変化
- お薬手帳の記載内容
- 客観的に観察できる情報
- 皮膚症状
- 浮腫の有無
- 歩行状態
- 認知機能の状態
検査値の記載ポイント
- 基準値から外れている検査値に注目
- 経時的変化を記載(上昇傾向、低下傾向)
- 薬物療法との関連性を考慮
記載例
O:
- アムロジピン5mg 1T 1×朝食後(前回から変更なし)
- ロスバスタチン2.5mg 1T 1×夕食後(新規処方)
- 血圧手帳確認:145/85mmHg(1週間前)→ 138/82mmHg(本日)
- 自己測定の血圧値は140〜150/80〜90mmHg台で推移。
- LDL-C 178mg/dL(3ヶ月前)→ 162mg/dL(先月、基準値130mg/dL以下)
- 両足首に軽度の浮腫を確認。
検査値や処方内容は単に記載するだけでなく、前回からの変化や基準値との比較など、評価につながる情報も含めるようにしましょう。
【A】Assessment:薬学的評価の書き方
Assessmentは、収集した情報(SとO)に基づいて、薬剤師が薬学的評価を行い、問題点を抽出する部分です。新人薬剤師にとって最も難しいと感じる部分かもしれません。
薬学的評価の視点
- 有効性の評価
- 治療目標に対する効果
- 症状改善の有無
- 検査値の改善状況
- 安全性の評価
- 副作用症状の有無と程度
- 検査値異常との関連
- 薬物相互作用のリスク
- アドヒアランスの評価
- 服薬状況
- 理解度
- 服薬上の問題点
問題点抽出のポイント
- 患者さんの訴えと客観的情報を総合的に判断
- 薬物治療の目標達成度を評価
- リスク因子を考慮(腎機能、肝機能、年齢など)
- 薬物動態学的・薬力学的相互作用の可能性
記載例
A:
1. 血圧コントロール:目標値(140/90mmHg未満)に近づいているが、まだ十分ではない。自宅血圧も高値傾向。
2. 脂質異常症:LDL-Cは改善傾向だが目標値未達。ロスバスタチン追加は妥当。
3. ロキソニンによる胃部不快感の可能性あり。NSAIDsによる胃粘膜障害を疑う。
4. 下肢浮腫はアムロジピンの副作用の可能性あり。
このように、複数の問題点を項目立てて、優先順位を付けて記載するとわかりやすくなります。単なる現状確認だけでなく、「なぜそう考えたのか」という臨床判断の根拠も含めるようにしましょう。
【P】Plan:薬学的ケアプランの立て方と記録
Planは、抽出した問題点(A)に対する具体的な対応策や今後の方針を記載する部分です。実際に実施した服薬指導内容や次回の確認事項なども含めます。
薬学的ケアプランの要素
- 薬物療法の最適化提案
- 処方提案(追加、変更、中止など)
- 用法・用量の調整提案
- モニタリング計画
- 副作用モニタリング項目
- 効果確認の方法と時期
- 次回確認すべき事項
- 患者教育・指導内容
- 実施した服薬指導の内容
- 生活習慣の改善アドバイス
- 副作用への対処法
記載のポイント
- 問題点ごとに対応策を明記
- 具体的かつ実行可能な計画を立てる
- 次回来局時の確認事項を明確にする
- 実際に行った指導内容を記録
記載例
P:
- 脂質異常症:ロスバスタチンの効果と副作用について説明。食後服用の重要性を強調。3ヶ月後の採血で効果確認予定。
- 血圧管理:自宅血圧測定を継続してもらい、1日1回以上測定するよう指導。食塩摂取量の減少を助言。次回来局時に血圧手帳を確認。
- 胃部不快感:NSAIDsの副作用について説明。医師に胃粘膜保護薬の追加を依頼する旨を伝達(疑義照会実施)。
- 下肢浮腫:浮腫の程度をモニタリングするよう指導。悪化時は受診を勧奨。次回来局時に確認。
- 医師へのフィードバック:胃部不快感と下肢浮腫について情報提供書を作成。
このように、各問題点に対して具体的な対応策と次回の確認事項を明記することで、継続的な薬学的管理につながります。新人薬剤師がよく陥る薬歴作成の5つの失敗例
新人薬剤師がよく経験する薬歴作成の失敗例と、その改善方法を紹介します。
失敗例1:事務的な記録になってしまう
悪い例
S: 体調良好。
O: ロキソニン錠60mg 3T 3×毎食後 14日分
A: 特に問題なし。
P: 用法用量を説明した。
改善例
S: 「先月から続いていた肩こりが良くなってきた」と自己申告あり。痛みの程度は10段階で8→4に改善。
O: ロキソニン錠60mg 3T 3×毎食後 14日分(前回から変更なし)
A: NSAIDsの効果発現が認められるが、完全に症状は消失していない。長期服用による胃腸障害リスクに注意。
P: NSAIDsの長期服用リスクについて説明。胃部不快感の有無を確認し、症状出現時は報告するよう指導。ストレッチ体操についても助言。
失敗例2:SOAPの要素が混在している
悪い例
S: アムロジピン5mg服用中。血圧高め。
O: 血圧手帳確認、服薬指導実施。
A: 降圧剤の効果不十分。
P: 塩分制限について説明した。
改善例
S: 「最近、朝の血圧が高めです」との訴えあり。めまい等の症状はなし。減塩に取り組んでいるが、外食が週3回程度あるとのこと。
O: アムロジピン5mg 1T 1×朝食後
血圧手帳:145-155/85-90mmHg(朝)、135-140/80-85mmHg(夕)
A: 朝の血圧値が目標値(140/90mmHg未満)を超えており、降圧効果が不十分。夕食時の塩分摂取が影響している可能性あり。
P: 外食時の塩分摂取を減らす具体的な方法(汁物を残す、醤油を控えるなど)を提案。2週間後の血圧値の変化を確認予定。
失敗例3:個別性の欠如
悪い例
S: 特に問題なし。
O: メトホルミン錠250mg 6T 3×毎食後
A: 2型糖尿病治療中。
P: 低血糖症状について説明した。
改善例
S: 「先日、昼食を抜いたら手が震えて冷や汗が出た」との訴え。症状は砂糖入りジュースを飲んで回復。最近、ダイエットのため食事量を減らしているとのこと。
O: メトホルミン錠250mg 6T 3×毎食後
HbA1c 7.2%(1ヶ月前)
A: 食事量減少に伴う低血糖症状の出現。メトホルミン単独では通常低血糖リスクは低いが、食事摂取不足により相対的な血糖低下が生じている可能性。
P: 低血糖の症状と対処法について再度説明。食事を抜かずに、1食あたりの量を調整する方法を提案。低血糖時の対応セットの携帯を推奨。食事記録をつけることを提案し、次回確認予定。
失敗例4:臨床判断の記載不足
悪い例
S: 咳が出る。
O: プラバスタチン10mg 1T 1×夕食後
A: 副作用の可能性。
P: 医師に相談するよう伝えた。
改善例
S: 「2週間前から就寝時に乾いた咳が出るようになった」と訴えあり。日中は症状軽度。痰や発熱はなし。花粉症等のアレルギー歴なし。
O: プラバスタチン10mg 1T 1×夕食後(2ヶ月前から服用開始)
リシノプリル5mg 1T 1×朝食後(2週間前に開始)
A: 咳の発症時期とACE阻害薬(リシノプリル)開始時期が一致。ACE阻害薬による空咳の副作用を疑う。スタチンでは一般的に咳症状は起こりにくい。
P: ACE阻害薬の副作用について説明。副作用疑い報告書を作成し、担当医に情報提供。ARBなど他クラスの降圧薬への変更を検討してもらうよう提案。
失敗例5:患者視点の欠如
悪い例
S: 内服コンプライアンス不良。
O: レボドパ・カルビドパ配合錠 3T 3×毎食後
A: 薬効が十分に得られていない。
P: 内服の重要性を説明した。
改善例
S: 「薬を飲むタイミングが難しく、時々飲み忘れる」と訴えあり。特に昼食時の服用が困難とのこと。パーキンソン症状は午後に悪化する傾向。独居で、薬の管理は自分で行っている。
O: レボドパ・カルビドパ配合錠 3T 3×毎食後
服薬状況:朝・夕はほぼ服用できているが、昼は週2-3回忘れるとのこと。
A: レボドパの服薬タイミングが不規則なため、症状コントロールが不十分。特に昼食時の服薬遵守率が低く、午後の症状悪化に関連している可能性が高い。
P: 一包化調剤の提案(朝・昼・夕で色分けし、視認性を向上)
これらの改善例を参考に、臨床判断と個別対応が明確になる薬歴作成を心がけましょう。
実践で使える!薬歴記入例と解説
ここでは、代表的な疾患・状況における薬歴の具体的な記入例を紹介します。これらの例を参考に、臨床現場での薬歴作成に役立ててください。
例1:高血圧症の初回来局時
S: 「先日の健康診断で高血圧を指摘され、今日初めて受診しました」とのこと。自覚症状はなし。これまで健康上の問題はなかったが、ここ数年血圧が上昇傾向とのこと。家族歴あり(父:高血圧、母:糖尿病)。飲酒習慣あり(日本酒1合/日)、喫煙なし。運動習慣なし。塩分摂取量は多め(麺類のスープを完飲するなど)。
O: アムロジピン錠5mg 1T 1×朝食後 28日分(新規処方)
診察室血圧:160/95mmHg(本日)
身長170cm、体重75kg、BMI 26.0
家庭血圧計は未所有
A: 本態性高血圧症:ステージⅡ高血圧に該当。生活習慣(塩分摂取過多、運動不足、飲酒)と遺伝的要因が原因と考えられる。
Ca拮抗薬の選択は初期治療として妥当。降圧目標は140/90mmHg未満。
服薬経験がなく、アドヒアランスリスクあり。
生活習慣の改善余地が大きい。
P: 高血圧の病態と治療目標について説明。
アムロジピンの作用機序、服用方法、起こりうる副作用(顔面紅潮、浮腫など)について説明。
家庭血圧計の購入を推奨。測定方法と記録の仕方を説明。
減塩方法(汁物を残す、加工食品を控えるなど)と適度な運動の重要性を説明。
次回来局時に血圧手帳を持参してもらい、経過を確認予定。
副作用発現時の対応についても説明。特に下肢浮腫の有無に注意するよう指導。
解説:初回来局時は特に詳細な情報収集が重要です。生活習慣や家族歴も含めて記録しましょう。また、新たに処方された薬剤についての説明内容も具体的に記載することがポイントです。
例2:糖尿病患者の処方変更時
S: 「血糖値が下がらないので、薬が追加になりました」とのこと。症状の自覚はないが、疲れやすさを感じることがあるとのこと。食事療法は実施中だが、間食(特に夕食後)が習慣化。自己血糖測定は週2回実施。直近の空腹時血糖値は130-150mg/dL台。
O: メトホルミン錠250mg 6T 3×毎食後(継続)
シタグリプチン錠50mg 1T 1×朝食後(新規追加)
HbA1c:7.8%→8.2%(3ヶ月前→先週)
空腹時血糖:145mg/dL(先週)
eGFR:72mL/min/1.73m²(1ヶ月前)
体重:68kg(3ヶ月前)→70kg(本日)
A: 血糖コントロール不良:HbA1c上昇傾向。目標値7.0%未満に対して乖離あり。
食事療法不十分:間食習慣と体重増加が血糖コントロール不良の一因と考えられる。
DPP-4阻害薬追加は妥当:作用機序の異なる薬剤の併用で血糖降下作用の増強が期待される。
低血糖リスク:メトホルミンとDPP-4阻害薬の併用で低血糖リスクは比較的低いが、食事摂取量の変動により相対的な低血糖の可能性あり。
腎機能は正常範囲内:現時点でメトホルミンの用量調整は不要。
P: シタグリプチンの作用機序、効果発現時期、副作用について説明。
次回来局時にSMBGデータと体重変化を確認予定。
低血糖症状と対処法について再確認。特に運動時や食事量が少ない時の対応を説明。
夕食後の間食を控える具体的な方法を提案(果物や無糖飲料への切り替えなど)。
SMBG(自己血糖測定)の頻度を増やすことを提案(朝食前と就寝前の2回/日)。
空腹時血糖値が継続的に180mg/dL以上となった場合は早めに受診するよう指導。
解説:処方変更時は、変更理由と新薬の説明に重点を置きます。検査値の推移も具体的に記載し、新たな薬剤追加による相互作用や副作用リスクも評価しましょう。
例3:副作用が疑われるケース
S: 「先週から咳が止まらなくて困っています」と訴えあり。特に夜間と早朝に乾いた咳が出現。痰はほとんどなし。発熱なし。風邪症状もなし。花粉症などのアレルギー歴なし。2週間前から血圧の薬が変更になったとのこと。
O: リシノプリル錠10mg 1T 1×朝食後(2週間前から開始、それまではカンデサルタン8mg)
アムロジピン錠5mg 1T 1×朝食後(変更なし)
アトルバスタチン錠10mg 1T 1×夕食後(変更なし)
血圧:132/78mmHg(本日、来局時)
咳の症状:就寝時と早朝に強く、日中は軽度。会話中にも時々咳込む様子が見られた。
A: ACE阻害薬(リシノプリル)による咳の副作用を強く疑う:
咳の出現時期とリシノプリル開始時期が一致
典型的な空咳で、夜間・早朝に悪化する特徴あり
感染症を示唆する所見(発熱、痰)がない
他の服用薬では通常このような咳症状は起こりにくい
血圧コントロールは良好:ARBからACE阻害薬への変更後も血圧は目標値を達成
患者のQOL低下:咳症状により睡眠障害が生じている可能性
P: ACE阻害薬の副作用(空咳)について説明。発生機序(キニンの蓄積)と出現率(約10%)についても情報提供。
副作用疑義照会書を作成し、処方医に情報提供。ARB(カンデサルタン)への再変更を提案。
咳症状は薬剤中止後1〜2週間で改善することが多い点を説明。
一時的な咳止め薬の使用は効果が限定的である点を説明。
次回来局時に症状の変化を確認予定。
その他の副作用の有無も確認したが、特に問題なし。
解説:副作用が疑われる場合は、症状の詳細と薬剤との関連性を明確に記載します。時間的経過や症状の特徴を詳細に記録し、薬学的な判断根拠を示すことがポイントです。
薬歴作成の効率を上げるテクニック
忙しい業務の中で質の高い薬歴を効率的に作成するためのテクニックを紹介します。
テンプレートの活用
疾患別・状況別のテンプレートを作成しておくと、記載漏れの防止と時間短縮につながります。
高血圧症患者のテンプレート例
S: 体調・自覚症状(めまい・頭痛・動悸など)
血圧手帳の記録頻度
降圧薬の飲み忘れの有無
塩分摂取・運動習慣の変化
O: 処方内容と変更点
血圧値(来局時・自宅測定値)
脈拍
浮腫の有無
検査値(K、Cr、eGFRなど)
A: 血圧コントロール状況の評価
服薬アドヒアランスの評価
副作用の有無と評価
生活習慣の評価
P: 服薬指導内容
生活指導内容
副作用モニタリング計画
次回確認事項
優先順位の明確化
全ての情報を同じ比重で記載するのではなく、臨床上重要な情報に重点を置きましょう。
優先すべき情報
- 処方変更点とその理由
- 新たに出現した症状や副作用
- 治療目標の達成状況
- アドヒアランスに関する問題
- 患者の特別な懸念や質問
効率的な情報収集のコツ
- 事前準備を徹底する
- 前回の薬歴を確認
- 検査値の変化をチェック
- 処方変更点を把握
- 質問の優先順位を決める
- まず開放型質問で全体像を把握
- 前回からの変化に焦点を当てる
- 重要な確認事項は漏れなく質問
- 記録の工夫
- 箇条書きを活用
- 重要なキーワードを強調(太字やマーカー)
- 数値データは表形式にまとめる
時短のための具体的アドバイス
- 患者との会話中にキーワードをメモする
会話しながら重要な情報をキーワードでメモし、後で詳細を記載すると時間短縮になります。 - 略語を適切に使用する
チーム内で共通認識のある略語を使用することで、記載時間を短縮できます。
例:BP(血圧)、HR(心拍数)、ADR(副作用)など - 段階的に記載する
まず骨子を記載し、後から詳細を追加する方法も効率的です。特に混雑時には有効です。 - 音声入力の活用
システムが対応している場合、音声入力を活用すると入力時間を短縮できます。
まとめ:薬歴は薬剤師の思考と成長の記録
薬歴は単なる法的記録ではなく、薬剤師の臨床思考の証であり、成長の記録でもあります。SOAP形式に沿った薬歴作成を通じて、臨床判断能力を高め、患者さんへのケアの質を向上させることができます。
薬歴作成の5つのポイント
- 患者中心の記録を心がける
患者さんの言葉をそのまま記録し、個別性のある薬学的ケアを提供しましょう。 - 臨床判断のプロセスを明確に
なぜそう考えたのか、評価の根拠を明確に記載することで、チーム内での情報共有が円滑になります。 - 継続的なケアを意識する
次回の確認事項を明記し、継続的な薬学的管理につなげましょう。 - 医療チームの一員としての視点を持つ
他の医療従事者が見ても理解できる記載を心がけ、多職種連携に役立つ記録を目指しましょう。 - 常に学び、更新する
新しい医薬品情報や治療ガイドラインを取り入れ、常に最新の知見に基づいた薬学的評価を行いましょう。
初めは時間がかかっても、継続的な練習と振り返りによって徐々に薬歴作成のスキルは向上します。先輩薬剤師からのフィードバックを積極的に求め、日々の業務を通じて成長していきましょう。
薬歴は、あなたの臨床判断の証です。患者さんの健康を守るために、質の高い薬歴作成を心がけてください。
薬歴がうまくなる書籍
FAQ
Q1: 薬歴に必ず記載しなければならない法的要件は何ですか?
A: 薬剤師法施行規則第16条の2に基づき、以下の内容は必ず記載する必要があります:
- 患者の基本情報(氏名、生年月日、性別など)
- 処方内容(医薬品名、用法・用量、処方日数など)
- 服薬指導の内容
- 患者の服薬状況
- 副作用の有無
- 併用薬・健康食品の使用状況
- アレルギー歴・副作用歴
- 患者の症状や状態
これらの情報が適切に記録されていないと、調剤報酬の算定対象外となる可能性があります。
Q2: SOAPとPOSの違いは何ですか?
A: POSは「Problem Oriented System(問題志向型システム)」の略で、医療記録の方法論です。SOAPはPOSの一部であり、具体的な記録形式を指します。POSは問題リストの作成、初期計画、経過記録(SOAP)、退院時要約などの要素から構成される包括的なシステムで、SOAPはその中の経過記録の形式です。薬局業務では主にSOAP形式が用いられていますが、これはPOSの考え方に基づいています。
Q3: 新人薬剤師が薬歴作成で最も注意すべき点は何ですか?
A: 最も注意すべき点は「臨床判断の根拠を明確に記載すること」です。単に症状や処方内容を記録するだけでなく、なぜそのような評価をしたのか、どのような薬学的問題があると考えたのかという思考プロセスを記載することが重要です。これにより、他の薬剤師が見ても理解できる薬歴となり、継続的な薬学的管理が可能になります。また、法的な観点からも、臨床判断の根拠が明確に記録されていることは重要です。
Q4: 薬歴の記載に時間がかかりすぎる場合、どうすれば効率化できますか?
A: 効率化のためのポイントは以下の通りです:
- 疾患別・状況別のテンプレートを作成しておく
- 患者との会話中にキーワードをメモする習慣を身につける
- 優先度の高い情報から記載する
- 箇条書きや表形式を活用する
- チーム内で共通認識のある略語を適切に使用する
- システムの機能(テンプレート保存、オートテキストなど)を活用する
ただし、効率化を追求するあまり、個別性や臨床判断の質が失われないよう注意が必要です。
Q5: 薬歴を通じて自分の臨床能力を高めるには、どのような工夫が有効ですか?
A: 臨床能力向上のためには以下の取り組みが効果的です:
- 定期的に自分の薬歴を振り返り、改善点を見つける
- 先輩薬剤師に薬歴の添削を依頼し、フィードバックを受ける
- 症例検討会などで自分の症例と薬歴を発表し、多角的な視点を得る
- 同じ患者さんの薬歴を時系列で見直し、介入の効果を評価する
- 関連する医学・薬学文献を読み、科学的根拠に基づいた記載を心がける
薬歴作成は単なる業務ではなく、臨床薬剤師としての成長の記録でもあります。常に学びの姿勢で取り組むことが重要です。
 もし転職計画があるなら当サイト経由してもらえると助かります。
もし転職計画があるなら当サイト経由してもらえると助かります。
ヤクタマが転職するときに毎度お世話になっているのが「ファルマスタッフ」ってサイトです。
転職サイトとしては忖度なしにヤクタマぶっちぎりでオススメです。
「ファルマスタッフ」は1つ1つの就業先をキャリアコンサルタントが必ず直接訪問して職場の状況ダイレクトにリサーチ!
そのため、求人情報が他社よりも濃い!職場の雰囲気や経営状況、残業などの忙しさなどのリアルを踏まえて転職先を提案してくれます。
エージェントさんに会ってみればわかりますが、とにかく真摯に向き合って対応してくれます。
今すぐ転職を考えている方もちょっと考え中の方も利用できます。すべて無料なので登録するなら当サイトから申し込んでいただければ幸いです。
公式ファルマスタッフ