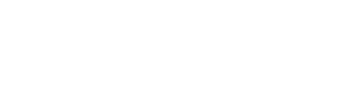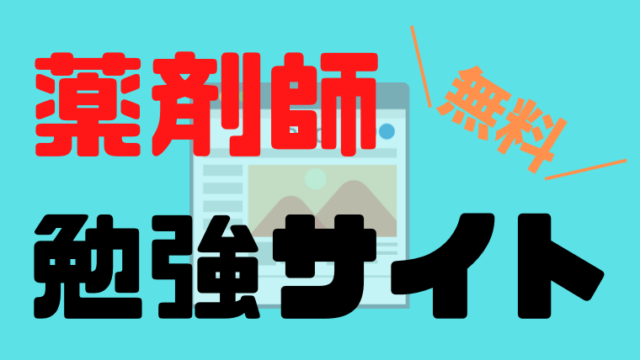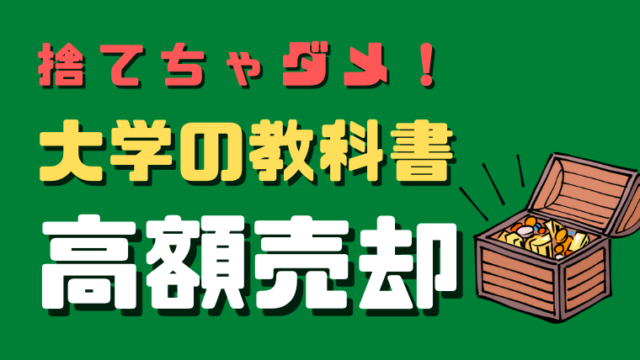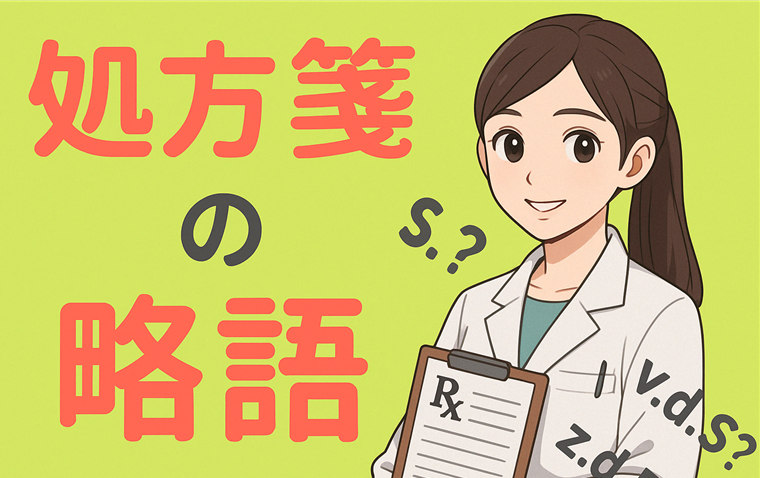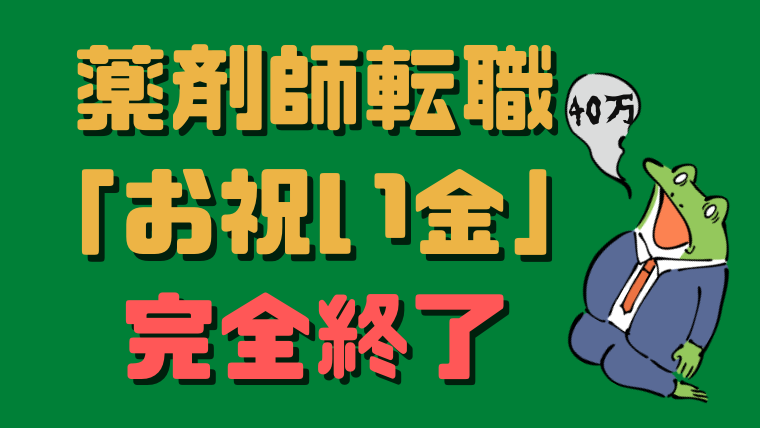どうもヤクタマです。
処方箋でアルファベットの略語を見て「これ何だっけ?」と戸惑った経験はありませんか? 略語の意味が思い出せないと調剤中に焦ってしまい、患者さんをお待たせしてしまうこともあります。
新人薬剤師の方は特に、「略語くらいサッと読めて当然」とプレッシャーを感じがちですよね。
でも大丈夫!処方箋に出てくる略語にはパターンがあり、ポイントさえ押さえれば怖くありません。
本記事では、薬剤師が覚えておきたい処方箋の略語を意味や由来とともにわかりやすく解説します。筆者も現役薬剤師として新人時代に略語に戸惑った経験があり、その経験から得たコツも交えてお伝えします。この記事を読めば、もう処方箋の略語で悩むことはなくなるでしょう!
服薬のタイミングに関する略語(朝・昼・夕・食前・食後 など)
処方箋では、服用する時間帯や食事との関係を示すために様々な略語が用いられます。代表的なものを以下に示します。
- M:Morgen= 朝。朝に服用する指示。
- N:Nachmittag= 昼。昼に服用する指示(※使用頻度は低い)。
- A:Abend= 夕。夕方(夜)に服用する指示。
- v.d.S:vor dem Schlafen= 就寝前。寝る前に服用する指示。
- v.d.E:vor dem Essen= 食前。食事の前に服用する指示。
- n.d.E:nach dem Essen= 食後。食事の後に服用する指示。
- z.d.E:zwischen dem Essen= 食間(食事と食事の間)。一般に前回の食後から約2時間後に服用します。
これら略語の由来はドイツ語が中心です。
昔は手書き処方箋でよく使われましたが、現在ではパソコン印字が主流となり「朝」「食後」など日本語で書かれるケースがほとんどです。
それでもベテラン医師(爺医)の手書き処方などで目にする可能性があるため、知っておいて損はありません。
また、a.c.(食前)やp.c.(食後)といったラテン語由来の略語が使われる場合もありますが、日本では上記のドイツ語略の方が一般的ですね。
服用回数・頻度に関する略語(1日○回や間隔の指示)
服用回数や服薬間隔を示す略語もいくつか存在します。主にラテン語起源で、1日に何回服用するか、何時間おきに服用するかを端的に表します。
- sid:semel in die= 1日1回。
- bid:bis in die= 1日2回。
- tid:ter in die= 1日3回。
- qid:quater in die= 1日4回。
- dieb.alt.:diebus alternis= 隔日(1日おき)に服用。
- omn.4hr:omni 4 hora= 4時間ごとに服用。
- 6st×4:6 Stunden ×4= 6時間おきに1日4回服用(”6st”は独語で6時間、”×4″は4回の意)。
これらの略語は欧米で使われる指示ですが、日本の処方箋では「1日○回」と日本語で記載されます。なお、略語ではなく数字と記号で表すケースもあります。例えば処方箋の用法欄に「3×」とだけ書かれている場合、1日3回(通常は朝昼夕)の服用を意味します。
医師によっては「毎食後」の代わりにこのような記載をすることもあります。
剤形・数量に関する略語(錠剤・カプセル・日数 など)
薬の剤形(剤型)や数量を示す略語もあります。こちらは英語由来のものが多く、薬の種類や投与量をコンパクトに表記するために使われます。
- O:Ointment= 軟膏(塗り薬の軟膏)。
- Cr:Cream= クリーム(塗り薬のクリーム)。
- Cap:Capsule= カプセル剤。
- Tab:Tablet= 錠剤。
- Syr:Syrup= シロップ剤。
- DS:Dry Syrup= ドライシロップ剤。
上記の略語は処方箋の薬名や剤形指定に付記されることがあります(例:「アモキシシリン Cap」など)。また、数量や日数の略語も以下のように用いられます。
- ○○C:数字+Cで**○○カプセル**という意味。例:「5C」は5カプセル分。
- ○○T:数字+Tで**○○錠**という意味。例:「10T」は10錠分。
- ○○Td:Tage Dosen= ○○日分という意味。例:「7Td」は7日分(1週間分)。
なお、○○Tや○○Cなど数字+略号は薬の総数を示すため、調剤時に読み間違えないよう注意が必要です。
その他の処方箋略語(Do処方、Rp.、EKC など)
上記以外にも、処方箋にはいくつか特殊な略語や記号が使われることがあります。ここでは代表的なものを紹介します。
- do(Do処方):Ditto(同じ)の略。前回と同一内容の処方箋であることを示すため、医師が処方箋に「Do」と記載することがあります(Do処方と呼ばれます)。
- Rp.:Recip(e)(レシピ:「取れ」の意味)より。処方箋の冒頭に書かれる略号で、処方の始まりを示します。欧米の処方箋様式に由来する表記で、日本の処方箋でも稀に見られます。
- EKC:Epidemic Kerato Conjunctivitis= 流行性角結膜炎(はやり目)の略。処方箋の備考欄などに赤字で「EKC」と書かれている場合がありますが、これは患者が感染力の強い流行性結膜炎であることを知らせる暗号です。処方箋の左上に赤い〇印がある場合も同じ意味になります。
以上、主要な処方箋略語を網羅しました。次に、これらの略語を扱う際に知っておきたい注意点を解説します。
略語を使う際の注意点
略語は処方内容を簡潔に伝えられて便利な反面、誤読や取り違えの原因になる恐れもあります。医師の筆跡が判読しづらかったり、似た略号がある場合は注意が必要です。そのため処方箋上の略記は原則として疑義照会(内容確認)の対象となります。実際、薬剤師法第24条でも処方箋に疑わしい点があれば調剤前に医師へ問い合わせて確認する義務が定められています。
現場では明確な略語(「M=朝」等)なら毎回問い合わせないこともありますが、少しでも不安があれば必ず医師に確認しましょう。患者さんの安全を第一に、疑問点を自己判断で済ませないことが重要です。
また、医療安全の観点からは処方箋に略語を使わない方が望ましいとされています。院外処方箋の記載要領でも「略語を使わず日本語で記載する」ことが推奨されています。略語や記号を用いる際には、誤解を生まない表記かどうか常に意識しましょう。
以上の点に注意しつつ、略語の知識を活かして正確かつ迅速に処方箋を読み取り、調剤に役立てていきましょう。
まとめ:略語をマスターして安全な調剤を
処方箋で使われる略語について、主要なものを解説しました。最初は覚えることが多く大変に思えるかもしれませんが、頻出する略語はごく一部です。
まずは朝・夕・就寝前など重要な略語を確実に覚え、その他は必要に応じて確認すれば問題ありません。略語の意味を把握しておけば、処方鑑査や服薬指導もスムーズに行えるようになります。
ぜひ本記事の略語一覧を現場で役立ててください。
よくある質問(FAQ)
Q. 略語は全部覚えないといけないの?
A. 全部を暗記する必要はありません。記事中でも述べたように、特に頻出する「朝・夕・就寝前(M/A/v.d.S)」だけは確実に覚えておき、他の略語は必要に応じて調べればOKです。実際、現場でもカンペを用意して参照しながら調剤している薬剤師も多いです。まずは重要な略語から優先して覚えていきましょう。
Q. なぜ処方箋の略語はドイツ語由来が多いのですか?
A. 日本の医学教育は明治時代以降、ドイツの影響を強く受けた歴史があります。そのため医療現場ではドイツ語由来の用語や略語が多く使われてきました。カルテ(診療録)用語や処方箋略語もドイツ語が基本となっており、M(Morgen)やA(Abend)などがその名残です。ただし近年は英語由来の略語も増えており、sid/bidのようにラテン語(欧米で使用)に由来する略語も混在しています。
Q. 「Do処方」とは何のことですか?
A. 「Do処方」は、前回と**同じ(Ditto)**処方を繰り返す場合に使われる表記です。患者さんの慢性疾患の治療で処方内容に変更がない場合などに、医師が処方箋に「Do」と記載します。これにより薬剤師は前回と同一内容の処方だと判断できます。
Q. 処方箋の略語が読めないときはどうすればいいですか?
A. 無理に推測で対処せず、必ず処方医に確認(疑義照会)しましょう。略語が判読できない、意味が不明な場合は調剤を保留し、処方箋を発行した医師に問い合わせて指示内容を確認するのが原則です。薬剤師法でも定められた義務であり、患者さんの安全のためにも遠慮せず確認することが大切です。明確な略語であれば慣習的に問い合わせない場合もありますが、少しでも不安があれば躊躇しないようにしましょう。
 もし転職計画があるなら当サイト経由してもらえると助かります。
もし転職計画があるなら当サイト経由してもらえると助かります。
ヤクタマが転職するときに毎度お世話になっているのが「ファルマスタッフ」ってサイトです。
転職サイトとしては忖度なしにヤクタマぶっちぎりでオススメです。
「ファルマスタッフ」は1つ1つの就業先をキャリアコンサルタントが必ず直接訪問して職場の状況ダイレクトにリサーチ!
そのため、求人情報が他社よりも濃い!職場の雰囲気や経営状況、残業などの忙しさなどのリアルを踏まえて転職先を提案してくれます。
エージェントさんに会ってみればわかりますが、とにかく真摯に向き合って対応してくれます。
今すぐ転職を考えている方もちょっと考え中の方も利用できます。すべて無料なので登録するなら当サイトから申し込んでいただければ幸いです。
公式ファルマスタッフ